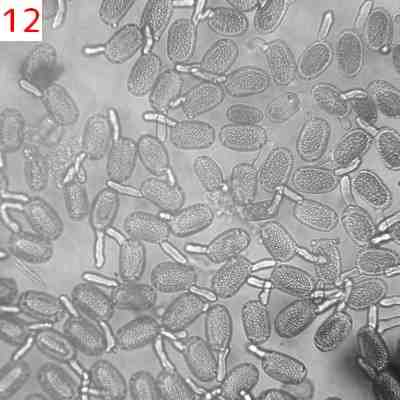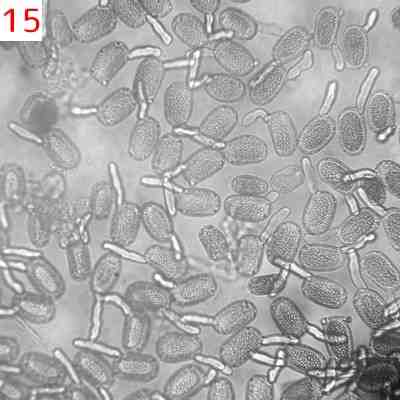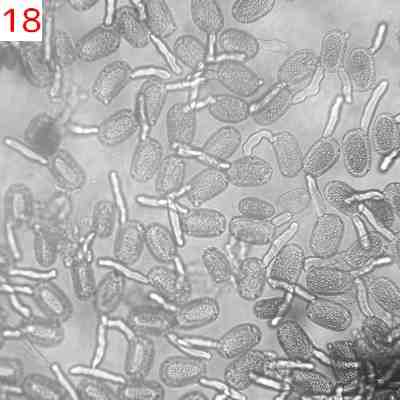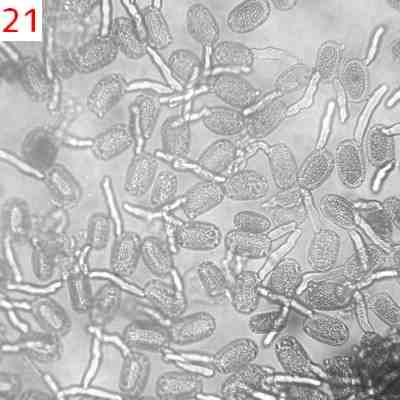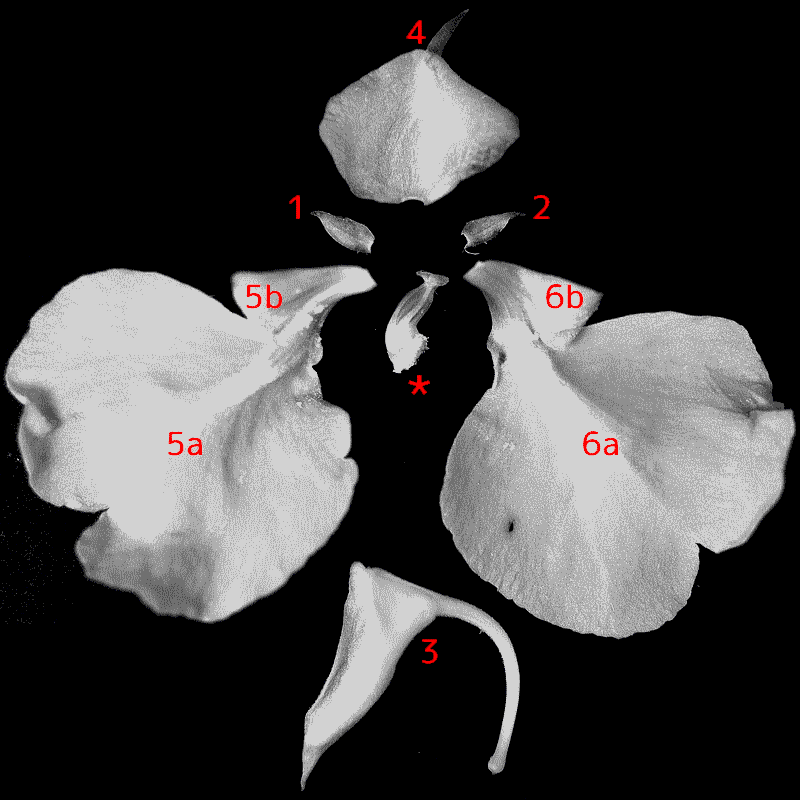
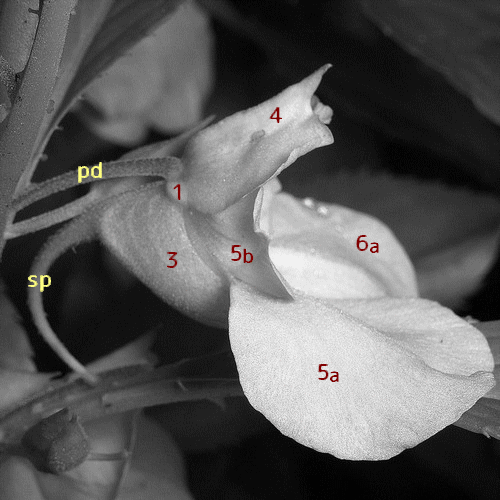
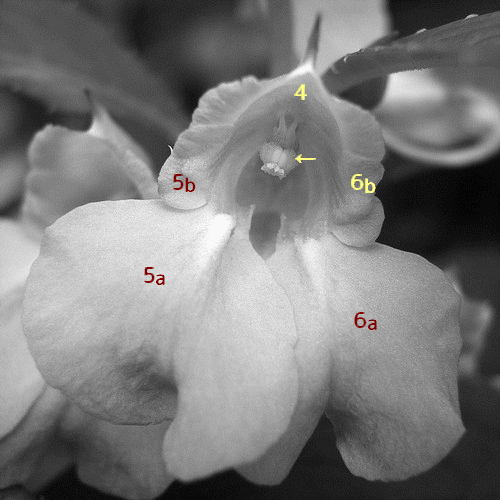
はたらきで区分すると、次のようになる。








ホウセンカを訪れるポリネーターは、「ひれ」に惹かれて訪れ、「ひれ」を足場にして「ラッパ」にもぐり込んで距の中の蜜を吸う。このときに、ポリネーターの背面に花粉や柱頭がくっついて送受粉が起こる。オドリコソウ(シソ科)やラン科など多数の被子植物が、ホウセンカと同じように、奥深く隠された蜜を求めて花の中に潜り込んだポリネーターの背面に花粉や柱頭をくっつけることで送粉を行っている。
ホウセンカは園芸植物なので、本来のポリネーターは原産地とされるインド~ミャンマーでないと決められない。同じ属で自生しているツリフネソウ類では、脚力が強くで長い口吻を持つマルハナバチ・スジボソコシブトハナバチが送粉している。
植えてあるホウセンカにもマルハナバチ・スジボソコシブトハナバチに加えてミツバチが来ていて、花粉や柱頭が背中に接触している。ミツバチの口吻はホウセンカの距と比べると短かすぎるが、届く範囲の蜜を吸っているのだろう(花粉カゴに花粉を集めるようすは見られない)。
 花にもぐり込むトラマルハナバチ
花にもぐり込むトラマルハナバチ 雄性期の花にもぐり込むミツバチ。胸部の背面に花粉が触れている。
雄性期の花にもぐり込むミツバチ。胸部の背面に花粉が触れている。

 長い口吻を持つスジボソコシブトハナバチ
長い口吻を持つスジボソコシブトハナバチ
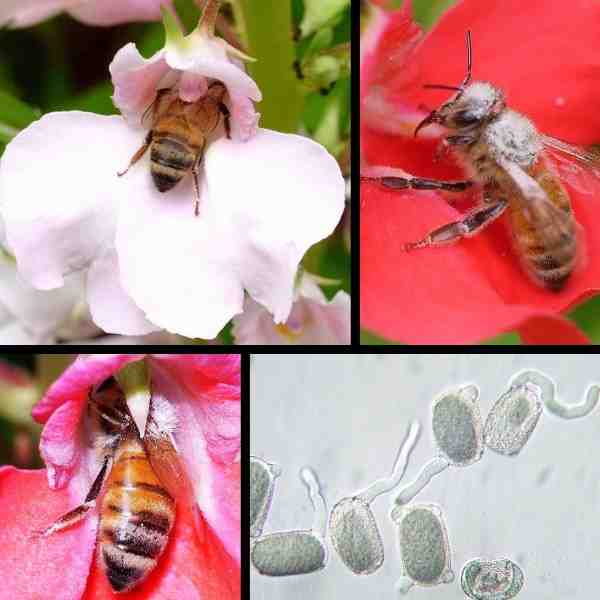 組図
組図
 つぼみの中から取り出した雄しべ・雌しべの先端部。5つの葯が組み合わさっているようすが分かる。
つぼみの中から取り出した雄しべ・雌しべの先端部。5つの葯が組み合わさっているようすが分かる。 開花直前になると、葯の先端が破れ、花粉が出始める。花糸に囲まれた緑色の部分は雌しべの子房。柱頭は葯に包まれたかっこうになっていて、外からは見えない。
開花直前になると、葯の先端が破れ、花粉が出始める。花糸に囲まれた緑色の部分は雌しべの子房。柱頭は葯に包まれたかっこうになっていて、外からは見えない。



 雄しべが取れると、初めて柱頭が露出する。
雄しべが取れると、初めて柱頭が露出する。
ホウセンカや近縁種は、花粉管の発芽・伸長の観察によく使われる。蒸留水や水道水の水滴表面に花粉を散りばめるだけで、短時間で発芽・伸長が起こる。他の多くのグループのように、ショ糖溶液(種によって違うが10%ていど)を使う必要はなく、溶液が蒸発しないように長時間保つ必要もない。発芽・伸長率もずっと高い。