選別の(あるいは、選別をしないことの)反映として、特定のグループのポリネーターに送粉される花は、送粉者と対応した複数の特徴の組み合わせ(送粉シンドローム[pollination syndrome])を示すことが多い。
 ウツボグサ(シソ科)の花を巡回するトラマルハナバチ
ウツボグサ(シソ科)の花を巡回するトラマルハナバチハナバチ[bee]はミツバチ科(ミツバチ・マルハナバチ・クマバチなど)・コハナバチ科・ヒメハナバチ科・ハキリバチ科などのグループを含む単系統群(共通の祖先から進化したグループ)で、蜜と花粉を集めて幼虫に与える生活をしている。ミツバチとマルハナバチは真社会性で、女王(クイーン)・雄・働き蜂(ワーカー)からなる家族集団(コロニー)をつくる。ミツバチでは、(スズメバチ+アシナガバチ)とアリ、シロアリと並ぶ大規模な家族集団が進化した。マルハナバチの家族集団は比較的小さく多くても数十個体程度だ。
ハナバチは、高い飛翔能力と器用で力強い脚、長いくちばし(口吻)を持ち、身体は花粉が付着しやすい毛で覆われている。ハナバチに送粉されることには、次のようなメリットがあると言われる。
ハナバチに大きく依存する花=ハナバチ媒花はしばしば次のような特徴を持つ。


ハナバチは蜜・花粉の両方を食料とするので、ハナバチ媒花以外のさまざまなタイプの花を訪れる。
野生植物や作物の結実は、ハナバチに大きく依存し、また、ハナバチの生存も野生植物や作物に依存する。両者の相利関係は、生態系や生物多様性の保全の重要な要素と考えられている。

チョウ・ガは液体を吸うのに適した長い口を持つので、チョウ・ガ媒花はハナバチ媒花と同じく蜜腺を花筒の底に隠していることが多い。しかし、他の特徴には多数の相違点がある。
チョウ・ガは狭いところに潜り込んだり花弁を押し下げたりすることができない。また、脚が細く、翅は鱗粉で覆わるためにハナバチと比べると花粉が付着しにくい。

 アカバナユウゲショウ(マツヨイグサ属)の花。T字形についた葯、つながった花粉が見える。
アカバナユウゲショウ(マツヨイグサ属)の花。T字形についた葯、つながった花粉が見える。
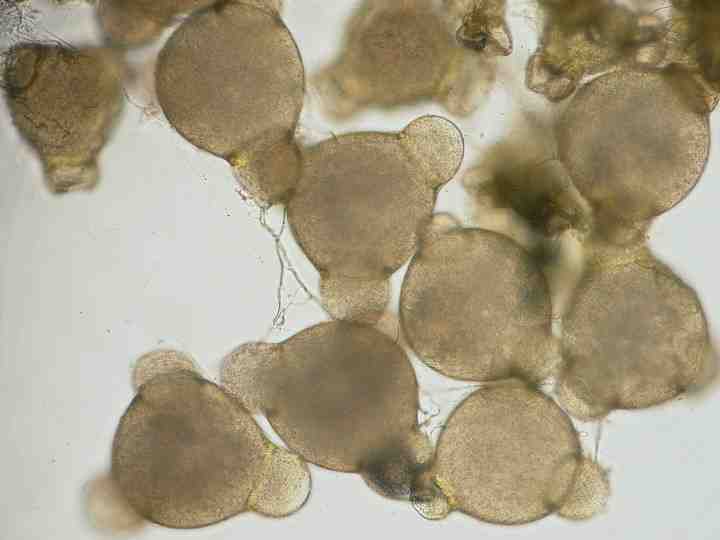
 ツツジ園芸種(オオムラサキ)の花で吸蜜しているジャコウアゲハ
ツツジ園芸種(オオムラサキ)の花で吸蜜しているジャコウアゲハ

 キアゲハがときおり羽ばたきながら吸蜜している
キアゲハがときおり羽ばたきながら吸蜜しているチョウ・ガ媒花の中で、夕方から朝にかけてスズメガに受粉されるスズメガ媒花は、白~明るい黄色の花、芳香など独特の特徴を持つ。カラスウリ類やマツヨイグサ類のように夜咲きで朝にはしぼんでしまうものが多いが、昼まで咲き続けてハナバチなど他の昆虫の訪花を受けるものもある。



キク科の頭花を構成する一つ一つの花は筒状で花筒内に蜜があるため、チョウ・ガがよく来る。花粉は頭花の表面に露出するため、甲虫やアブも来る。


チョウ・ガ媒花の特徴を持つ花でも、ハナバチの訪花はしばしば見られる。



 ケブカハナバチが吸蜜している。
ケブカハナバチが吸蜜している。 ツツジの園芸品種(オオムラサキ)を訪花するケブカハナバチ
ツツジの園芸品種(オオムラサキ)を訪花するケブカハナバチ赤~朱色、厚みがあって丈夫な花冠、多量にたまった濃い蜜が共通する特徴だ。
吸蜜する鳥には、ハチドリのようにホバーリングしながら吸蜜するものもいるが、枝に止まって吸蜜するものも多い。後者の場合、「止まり木」が必要で、太い枝に花が直接ついたり(オオバヤドリギ・マツグミなど)、花序の軸が太くて丈夫だったり(アロエなど)する。


鳥類の中で花蜜を主食とするグループとしては次の3つがあり、それぞれ別々に進化したと推定されている。

 カンザクラ(バラ科)から吸蜜するメジロとヒヨドリ
カンザクラ(バラ科)から吸蜜するメジロとヒヨドリ
日本には花蜜専門の鳥は分布しないが、メジロやヒヨドリなどの吸蜜が、特に他の餌が乏しい早春に、市街地でも容易に観察できる。
その他の例→鳥媒花